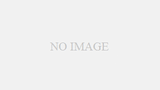先週は「バイアスを受け入れることは、苦しいこと」と題して、葛藤について書きました。妻がそれを助けてくれている、と。今週もまた週末から週明けにかけて家族と熊本で過ごし、私と妻は何度も対話を重ねました。私たちの葛藤は、現在進行形なのです。
自分以外の誰かを、助けることなどできない
「自分以外の誰かを、助けることなどできない」
今回の対話の、テーマの1つがこれでした。「これを受け入れることから始まる」と、妻に言われました。私は、簡単には受け入れることができませんでした。
妻は、現在福祉の仕事をしています。
福祉の課題には、解決や答えが本質的にはありません。短期的に解決したように見えても、長期的にはそうでもないことがある、あるいは、ある側面からは解決したように見えても、別の側面で新たな課題が見つかる、ということがあるからです。そして、そもそも解決や答えと感じるのは主観であり、支援者にそう感じられても、当事者(被支援者)には、そう感じられていない場合も、少なくない、と言うのです。そして、それを切実に感じた被支援者としての経験を、妻自身が持っていました。
「私と同じ思いを、誰にもして欲しくない」
そう、妻は強く願っています。
だから「調子に乗れない」のだと妻は言います。
なるほど、理屈としてはよくわかります。論理的には「支援には終わりがない」ことを意味します。私は、それを想像すると、苦しくなりました。「どうしているのか」と私が尋ねると、
「忘れることがなく、いつも気に掛け、また気に掛かっている」
と、教えてくれました。
私は、それでは苦しいのです。だから私は、気に掛け続けることが苦手です。妻は、しようとしてそうしているのではなく、「自然にそうなる」のだと言います。ゆえに、私が感じるような苦手意識や苦しさを、妻は感じてはいないようなのです。
逆の立場で互いを理解しよう思い、次のように妻に尋ねました。
「(私が得意で)自分は苦手で苦しいと思うことを1つ教えて──」
しばらく考え込んだ末に妻は「地理!」と言って、次のように答えました。
「白紙に日本地図を描いて、都道府県名と県境を描き入れていくこと」
その作業を想像すると、私は苦ではなく、むしろ「楽しそう」とさえ感じて、ニマニマします。妻は答えを説明しながら、もうすでに顔をゆがめており、如何にも苦しそうでした。私と妻は、互いの感覚を理解し、想像し合うことができました。
取りこぼしている人がいる
私が、1対多で何か──例えば講演など──をするとき「(私が)取りこぼしている人がいる」と妻は感じているのだそうです。妻は、その人たちに自然に意識が向かうので、ほぼ必ず気づくことができるのです。
言われてみれば確かにそのとおりで、全員に同じように受け取ってもらえているとはさすが思えず、受け取り方に差があることを薄々感じてはいました。
「ある程度は仕方がない……」
そうやって線を引くことを、自分の心の保護を言い訳にして、私は正当化してきました。それは、「できない」ことを受け入れているのとは決定的に違います。受け入れるのが苦しいから「できない」ことを正当化し、受け入れることを強いられないように逃げてきたに過ぎません。
「自分以外の誰かを、助けることなどできない。これを受け入れることから始まる」
妻が、気づいて欲しいと願っていることの1つ目の側面が、この「1対多での取りこぼし」です。
違う世界で生きてきた私たち
では、1対1ではどうか。
事象を自分に都合よく解釈し調子に乗りやすい私を、妻が教え諭してくれました。
私は、他者との関係性を避けて生きてきました。自分を守るためでした。だから「関係性とは無縁でよい」と私は考えていました。しかし妻に言わせれば、
「“ない”ことも、関係性。だから“関係性がない”というのは矛盾であり思い込み」
なのだそうです。目から鱗が落ちました。つまり私は「“ない”という関係性」で他者と関わって生きてきていたのです。
対する妻は、真逆とも言える世界で生きてきました。「“ある”しかない関係性」あるいは「”ない”がない関係性」の世界です。その世界を妻は、かつてこう説明してくれました。
「目の前に複数の人がいると、自分も含めたその人たち同士の関係性が線になって見える。というか、そうしか見えない」
CGのようにしか思えない世界。私には、頭の中にぼんやりと思い浮かべるのが、やっとでした。その世界で生きる妻は苦しくもあるそうで、「“ない”という関係性」があることを羨ましくも思うそうです。
そんな「“ない”しかない関係性」という世界で生きている私は、それ自体を受け入れていませんでした。「“ない”しかない関係性」にありながら、他者との関わりを求めてもいます。それは「私にとって良い」関わりであり、自分勝手な関わりです。私が肯定される関わりであり、私が認められる関わりです。その関わりを求め、そうでない──私が否定され、私が蔑まれ、私が攻撃される──関わりを避けようとするあまり、私は「余計なこと」をします。
その「余計なこと」の1つが、「自分以外の誰かを助ける」という、できもしないことなのです。
妻が最初に感じた「本来の私」
妻の、私への最大級の賛辞の1つがこちらです。
「“ない”しかない関係性という世界で生きられているあなたは、“ある”という関係性の影響を受けることなく、ただ真っ直ぐに自分の興味へ集中することができる」
妻は「私が書いた文章」で私に出会いました。
文章を書いている時の私は、まさに「“ない”しかない関係性」の世界に生き切れています。ゆえに「余計なこと」に目を奪われる心配がほぼありません。そんな、妻が言うところの「本来の私」だけがほぼ純粋に出ているでろう「私の書いた文章」で私に出会った妻は、最初に「本来の私」を感じられたわけです。
しかし、私は「余計なこと」をする。
妻にしてみれば、残念でしかありません。これまでも、手を替え品を替え、このことを私に伝えてきた妻ですが、私の抵抗が強く、今日に至っていました。
受け入れることを抵抗する私に、妻は次のように諭して、強ばりを緩めてくれました。
「“私にはできません”と言った時、否定されたり、攻撃されたりしても良い。相手のそのエネルギーは、次の人を探す原動力になるから」
「あなたが見えてないだけで、この世界にはたくさんの人がいる。心配しなくても誰かがなんとかしてくれる」
「本来のあなたができること、あなただけができることに、真っ直ぐに集中できたら──」
「自分以外の誰かを、助けることなどできない。これを受け入れることから始まる」
妻のおかげで、私もようやくスタートラインに立てたのかもしれません。
1対1では「余計なこと」にまで欲張らず、自分の役割に集中する。
1対多は、必ず妻と2人で行う。妻が取りこぼすことなく全員を見てくれるので、私は安心していつもどおり集中することができる。
受け入れた先に見えてきたのは「集中」でした。
今日の気づき
自分以外の誰かを、助けることなどできない
受け入れた先に見えてきたのは「集中」でした
長谷川高士「受け入れた先に見えてきたのは「集中」でした」『メールマガジン【前進の軌跡】』第218号,2022年7月5日(2022年7月8日改稿)