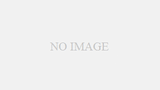このところ〈偏見〉について考えるきっかけが数多く起きています。「偏見」を辞書で引くと「かたよった見解、中正でない意見」(1)とありました。きっかけが数多く起きているというよりも、私のアンテナの感度が上がったのかもしれません。つまり、気づきやすくなったのです。
アンテナの感度が上がった理由の1つに、法律の勉強があります。司法試験予備試験の勉強をし始めてから半年、初めて触れる法学は「答えのない」世界でした。対象となる事柄には、互いに相反する複数の立場や視点が常にあり、それを偏ることなく中正に取り扱うことが求められます。法学を学ぶことは、偏見を正す以前の、偏見の存在に気づくトレーニングでもあるのです。
(1) 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年
バイアスが先手を取ると強い
心理的な反応として認知の偏りや歪みを捉えるとき、それらを〈バイアス〉とも呼びます。具体的には、思い込み、先入観、錯思・錯覚、等。〈偏見〉と〈バイアス〉は、互いに重なるところがあります。〈バイアス〉に影響を受けて表明された意見や見解が〈偏見〉と言えるでしょうか。偏見に気づくことは、すなわちバイアスに気づくことだと言えそうです。
〈バイアス〉それ自体は、善悪で評価すべき対象ではない、と私は考えます。ヒトとして正常な心理的反応であり止めようがないから、そしておそらくは、心身を守るために獲得した特性であろうから、です。〈バイアス〉に影響を受けて生まれた〈偏見〉が、適切ではない判断を生む、あるいは他者を不当に傷つける。これら「適切ではない判断」や「他者を傷つけること」は、悪いと評価される確度が極めて高いと言えます。要するに、きっと悪い。ここまでは割と冷静に確認し合うことができるのです。
しかし、問題はここからです。〈偏見〉に基づく不適切な判断や他者への中傷を咎めるとき、後手は大いに不利である、という仮説を私は持っています。先手を打った相手が影響力のある者──例えば、人気のある有名タレントや大手マスメディアなど──であれば、なおさらです。身近で言えば、いわゆる「声の大きい人」をイメージしてもらえば、分かりやすいかもしれません。
先手は言います。
「●●って、おかしくないですか?」
と。質問の形式をとってはいますが、「おかしい──あるいは、間違っている──でしょ」と同意を強く求める表現です。もしも「●●が間違いである」という意見が、〈偏見〉であった場合、それに影響を与えた〈バイアス〉を共有する多くの人々は、この先手に共感し同調します。
質問を受けた後手は、答えるほかない状況です。繰り返しますが「●●が間違いである」という先手の意見が〈偏見〉であり、実際には間違いではない、あるいは間違いとは言い切れない場合、後手は、こう答えるしかありません。
「いいえ、おかしくありません」
はい、で始まる、質問を肯定する答えに比べて、いいえ、で始まる、質問を否定する答えは、受ける印象(エネルギー)が弱いと感じます。否定せざるを得ない質問を投げかけること自体がすでにフェアではないのです。
続けて、先手はこう尋ねます。
「えー、何でですか? 何でおかしくないんですか!?」
大事なので三度繰り返しますが、あくまでも先手の意見が〈偏見〉であり、その全部または一部に正すべき誤解がある場合を想定した思考実験をしています。この質問を受けた後手は、理由を説明するよりほかありません。客観的に両者を見ると、さらにバランスが不当に不均衡である様子が見てとれます。
誤解している側が、正解している側にその理由を尋ねているにもかかわらず、なぜか勢いは誤解している側の方が強い。多勢に無勢で、正解している側は劣勢に立たされています。元のバイアスの影響を受け続けているこの状況では、実は正論で答えているのにもかかわらず、なぜか言い訳のよう聞こえてしまう。これも聞き手の認知バイアスと言えるかもしれません。そして最後は、先手にこう締めくくられます。
「えー、でもやっぱりおかしいでしょ」
それ以前のやり取りの一切を帳消しにする、身も蓋もない言葉です。
バイアスを受け入れることは、苦しいこと
さて、皆さんは先手と後手、どちらを経験することが多いでしょうか。または、どちらに共感するでしょうか。私は、後手の立場、あるいは後手を応援する立場になって、この文章を書いていました。しかし書きながら、私自身が気づかずに先手になっているであろうことを想像し、身震いしました。互いに自身のバイアスの影響を大いに受けており、1つの議論においてさえ、先手と後手は、きっと容易に入れ替わり得るのだろうと思いました。
バイアスを受け入れる。やり取りの不当な不均衡を解消し、適切な均衡で対話を深められるには、バイアスの存在を1人1人が受け入れることが必要だと思います。
「●●って、おかしくないですか?」
この先手の初手は、すでにバイアスの影響を受けています。自身の意見を絶対正として同調を半ば強要するこの構文の使用を禁止し、意見を表明したい場合は肯定文を使用し、かつ理由を添える。
「●●はおかしいと思います。なぜなら▲▲だからです」
このルールに基づけば先手が不均衡に有利になることを抑制できそうです。しかしお察しのとおり、これは非現実的であり、綺麗事でしかありません。
次は、先手の2手目です。
「いいえ、おかしくありません」
こう後手から返ってきた答えを、
「あっ、おかしくないですか」
と、先手が受け入れる。これも本来あるべき姿勢であり、これにより両者の均衡は正当に保たれそうです。しかし、やはりこれも非現実的。それができるのならば、そもそも初手で「おかしいでしょ」と攻めて──あるいは、責めて──はいないでしょう。
さて、どうしたものか……。これが私の葛藤です。より深く葛藤しているのは、後手ではなく先手としての立場の自分に対して、です。私を助けてくれるのは、やはり妻でした。妻は臆することなく、私のバイアスに直にアプローチしてくれます。それはかなりのストレスが妻にもかかることだと思いますが「それしか選べない」という特性を妻は持っています。妻は、苦しいと思います。
バイアスを受け入れる私もまた苦しい。例えるならば指の爪を剥ぐような感覚です。必要性と正当性を確信し、痛みを想像するあまり、覚悟が定まりません。
剥ぐという覚悟が決まれば、その瞬間に「あってもなくてもよいもの──これは例えの限界で、爪が必要であるのは言うまでもありません──のだ」とわかり、こだわりを手放せる。覚悟が決まるということが、受け入れるということなのだと思います。
「これ以上、苦しめたくはない」
妻に対するこの思いが、私の覚悟を後押しします。昨晩から今朝にかけて、覚悟を決めてバイアスを受け入れ、また1つ偏見を手放すことができました。一緒に葛藤してくれる妻に、心から感謝しています。また1歩、前に進みました。
今日の気づき
バイアスを受け入れることは、苦しいこと
妻に対する思いが、私の覚悟を後押しする
長谷川高士「バイアスを受け入れることは、苦しいこと」『メールマガジン【前進の軌跡】』第217号,2022年6月28日(2022年7月1日改稿)
引用・参考文献一覧
- 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年