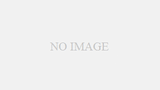「豪雨時には、逆流対策としてトイレに水のうを」
このようなメッセージがこの数年で徐々に定着しつつあります。ところが……いまいちピンと来ない。「トイレから排水が逆流する」というイメージに未経験の人であれば、実感がわきづらいのではないでしょうか。
かく言う私もその1人。加えて、専門家として構造や仕組みを知っている分だけ、「本当にそんなことになるのか」と、むしろ余計に懐疑的になる一面がありました。
そんな話をしていると、妻が衝撃のひと言を口にしました。
「私は、そういうもんだと思ってたよ。だって経験したことあるもの」
なんと妻は、子どもの頃に浸水被害を経験していたのでした。しかも、
「少なくとも2回以上はある」
と、言うではないですか。生まれてこのかた間近で浸水を経験したことがない私は驚きました。
他にも、複数の方から「豪雨時の逆流対策」について質問を受けたこともあり、今回はこれをテーマに書きたいと思います。「豪雨時にトイレ等から排水が逆流する」というリスクの高さは、一体どの程度のものか。水のうなどの対策は、本当に必要なのか。この問いを考察します。
「一様ではないリスク」をどう捉えるか
この問いに、結論的に答えるならば、次のようになるでしょうか。
「対策するに越したことはないが、リスクは一様ではない」
ゆえに、
「リスクのアセスメント(評価)には、個別の条件が必要である」
よって、
「一般論では答えられないので、個別に相談してください」と。
こんな何とも歯切れの悪い答弁にならざるを得ないのが、この問いなのです。
およそ日本に住む者ならば、地震による家具の転倒には十分に注意を払い、防止の対策を施すべきである。あるいは、到達時間や浸水深などの津波の危険度は、場所さえ分かればすぐにでも知ることができる。この2つは、明言できる内容です。
しかし、家具の転倒リスクほどに一様でもなく、津波のリスクほどに度合いが明確でもない。「豪雨時の排水逆流リスク」とは、そういうものなのです。
理由は明らかです。条件となる因子(ファクター)が複数あるからです。冒頭のとおり「豪雨時の排水逆流リスク」について啓発する情報はあまたありますが、この点、つまり条件となる因子が複数ある、という点にまで踏み込んでいる情報は、ほとんど見当たりません。
この理由も明確です。一般論では答えられないから、小難しい話になることを避けられないから、です。小難しい話は避けたい。ゆえに、条件をスパッと無視して「豪雨時には、逆流対策を」となりがちなのです。時にはそれも必要でしょうが、常にそんな大味な表現で本当に良いのだろうか、と私は思います。例えるならば、内陸部も含む日本中のどこに住んでいる人にも、等しく津波対策を求めているようなものではないだろうか、と。私は以前からこんな課題を意識していました。
課題を乗り越えるには、小難しい話になることを避けられません。でも、心配は無用。このメルマガは小難しい話を避けるどころか、普段からむしろ好んで書いているから。そして、それを承知で読んでもらえることを期待できるから、です。
逆流とは何か──2つの逆流を考える
そもそも逆流とは何か。まずはここを押さえておきたいと思います。いつも通り辞書を引くと、「水が通常とは反対の方向に流れること」(1)と、ありました。自分を起点にしたとき、起点から離れる方向が排水の通常の流れです。よって、排水が「通常とは反対に流れる」とは、起点である自分の方へ排水が近づいてくることを意味します。これ──すなわち「排水が自分の方へ近づいてくること」──が、排水の逆流です。
排水の流れを担保しているのはパイプや機器などの排水設備です。パイプという流路があるから排水は流れられるのであって、流路がなければ排水は排水たり得ない。つまり排水と排水設備は不可分であり、排水設備なしに排水が存在することはあり得ません。
たとえばトイレであれば、便器から「水があふれた」ことをもって、「排水が逆流した」と、私たちは認識するでしょう。このときの逆流の原因としては、排水設備の構造上、次の2つが考えられます。
- 1)文字通り、水が逆に流れてきた
流路の最下流から起点に向かって排水が遡上して「あふれた」という場合。 - 2)先が行き止まっていた
何らかの理由で流路が行き止まっていたところへ、さらに水を流した、あるいは流れたことにより「あふれた」という場合。
1)と2)のいずれも、目の前で起きている「あふれた」という現象は同じであり、排水が自分の方へ近づいてくるので「逆流」だと言えます。しかし両者には違いがあります。1)が何もせずに起きたのに対して、2)は「さらに水を流した」ことで起きました。換言すれば「あふれた」か、「あふれさせた」か、の違いです。
実際には、豪雨時において両者は「まったく別々のもの」というわけではなく、1)が2)になることも、あるいはその逆も、状況によっては十分にあり得ます。それでもあえて、「排水の逆流」だと私たちが認識する「あふれた」という結果を、「それに影響した人為的なきっかけがあったか、なかったか。その有無によって分けて考えよう」と、私は提案したいのです。
(1) 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年
「大雨が降るとどうなるか」を考える
大雨が降るとどうなるでしょうか。地面や建物が水に浸(つか)る「浸水」が起きます。この「浸水」の起き方にも大きく分けて2種類あると言えます。2つの違いをひと言で言えば、「(堤防を乗り越えて、または堤防が切れて)河川の水があふれたかどうか」です。あふれた場合の浸水被害を「外水氾濫」、そうでない場合を「内水氾濫」と呼びます。
- 〈1〉外水氾濫
河川の水があふれることで起きる浸水被害。いわゆる洪水のこと。 - 〈2〉内水氾濫
河川の水はあふれていはいないが、増水により雨水排水の流れが阻害されるなどして起きる浸水被害。河川が増水していなくても降雨量が甚大で、排水の能力を大幅に超えただけでも起き得る。
水害というと、得てして私たちは〈1〉の浸水被害をイメージしがちであり、自治体が作成する洪水ハザードマップもその多くが〈1〉を想定しています。しかし〈2〉の浸水被害も実際に発生しており、近年それが増加傾向にあると言えます。このことから〈2〉の内水氾濫を想定したハザードマップの作成も、強く求められている(2)のです。
(2) 時事通信社「「内水氾濫」ハザードマップを=広域浸水受け、自治体に通知―国交省」『時事ドットコム』,2019年11月9日(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_disaster20191109j-03-w280,2022年7月2日情報取得)
雨水排水が生活排水路に浸入する可能性
次の問いです。
「生活排水と雨水排水は、混ざり得るか」。別の言い方をすれば、「雨水排水が生活排水路に浸入し得るか」という問いについて考えてみましょう。冒頭の問いと同じく「一般的には答えられず、条件による」というのが答えです。「による」とされるこの条件には、大きく分けて次の3つがあります。叙述上の都合から、これらを「下水道条件」と呼ぶことにします。
- 条件【1】 公共下水道に接続していない
- 条件【2】 公共下水道(合流方式)に接続している
- 条件【3】 公共下水道(分流方式)に接続している
これらの3つは、2つ以上が同時に成立し得ず、それぞれが独立した命題です。また現在の日本において水洗トイレを使用している住宅であれば、いずれか1つには必ず当てはまるという、例外のない条件でもあります。
「雨水排水が生活排水路に浸入し、両者は混ざり得るか」という問いの答えは、上の「下水道条件」を入力すれば自ずと出ます。入力する条件と出る答えの対応は次のとおりです。
- 【1】【2】はあり得る
- 【3】は構造上あり得ない(がゼロとは言い切れない)
理由は単純です。【1】【2】は、生活排水と雨水排水がその流路を直接共有しており、1本のパイプ──あるいは側溝等──で流れるのに対して、【3】には両者による流路の共有がなく、最後まで別々のパイプで流れきるからです。
【1】から【3】までの下水道条件は日本において水洗トイレを使用している住宅であれば、いずれか1つには当てはまるという例外のないものでした。同時に、2つ以上が同時に成立し得ない独立した命題でもありました。【1】から【3】までが、それぞれ全体に対してどの程度の割合であるのかを示すことは可能ですが、個別(戸別)にみればその割合にさしたる意味はありません。「どれかが選ばれ、またどれかしか選べない」という時点で、特定の個(戸)においては、その結果が100パーセントだからです。
下水道条件が【1】から【3】のどれに当てはまるか。豪雨時の排水逆流のリスク評価には、この情報が必須です。
逆流と浸水の「下水道条件」との関係性
〈2〉の内水氾濫は、1)または2)、あるいはその両方の逆流が発生した結果である、と説明できます。すなわち、増水した水が雨水排水管へ流れ込み、遡上して道路の排水口から「あふれ」出すこと始まる浸水被害と、河川が増水したことなどが原因で雨水排水の流れが阻害され、河岸周辺の地域に降った大量の雨が道路の排水口を「あふれ」させることで始まる浸水被害です。前者が1)の逆流であり、後者が2)の逆流です。
〈2〉の内水氾濫時において、1)または2)の逆流が起きて、トイレなど生活排水の排水口から排水があふれる恐れがあるのは、構造上は、下水道条件が【1】と【2】のときだけです。下水道条件が【3】のときは、生活排水路への雨水排水の浸入を考えにくく、1)および2)の逆流は、設計上は、共に起き得ないはずなのです。
では、浸水してしまった状況ではどうでしょうか。浸水は、厳密には建物が水に浸かることを指しますが、建物が水に浸かっているとき、当然にその周りの地面も水に浸かっているはずです。そのため本稿では、浸水を「地面や建物が水に浸かること」と理解して進めます。
地面や建物が水に浸かっていれば、雨水排水路は満水に近い状態でしょう。その場合、下水道条件が【1】または【2】であれば、流路を共有する生活排水路もまた満水に近く、その水位は浸水深と同じレベルに、物理的にはなるはずです。
もしも浸水深が床下まで到達していれば、1)の逆流によりトイレなど生活排水の排水口から排水があふれる危険が間近に迫った状態、そして2)の逆流により、トイレで水を流せば排水があふれる条件を十分に満たしている状態である、と言えます。
では、下水道条件が【3】、すなわち分流方式の公共下水道に接続している場合はどうでしょうか。実はこれ、……分からないのです。分流方式の排水設備が、そんな状況を想定して設計ないし施工されてはいないからです。
排水管路は外部に対しては密閉されているため、地面が浸水──すなわち、水没──しても、構造上は、外部から生活排水路内へ、浸水した水が流入することは考えにくいのです。しかし浸水深が深ければ深いほど大きな水圧が生活排水路にもかかり、何らかのきっかけをもって、浸水している水が生活排水路内に浸入することもあるかもしれません。
こんな事例があります。2022年6月、イチローさんの出身地としても知られる愛知県西春日井郡豊山町で、珍しいトラブルが起きました。下水道管に設置された逆流防止用のゲートが故障により閉じてしまい、下水道が流れなくなるというトラブルです(3)。
この逆流防止用ゲートは、河川を横断する下水道管の、横断部分の前後に設置されていました。河川内を横断する下水道管には、地震等で破損すると、その破断部から下水道管内に河川水が浸入するという「逆流のリスク」が想定されます(4)。このゲートの役割は、このリスクを緊急的に防ぐことであり、それを意図して設置されていました。
このようなリスクも含めて、たとえ下水道条件が【3】、すなわち分流方式の公共下水道に接続している場合であっても、すでに浸水している状態ならば、1)および2)の逆流は、
「分からないながらも、起こり得る」
と考えた方が、どうやら良さそうなのです。
(3) 愛知県「豊山町(豊場地区)の下水道利用制限のお願いについて(ページID:0404368)」,2022年6月6日(https://www.pref.aichi.jp/press-release/toyoyama-gesuiseigenn.html,2022年7月2日情報取得)
(4) 毎日新聞社「下水道トラブル 5000世帯に排水減要請 愛知・豊山」『毎日新聞デジタル』,2022年6月8日(https://mainichi.jp/articles/20220608/ddq/041/040/003000c,2022年7月2日情報取得)
妻の体験の答え合わせ
以上の考察を踏まえて、妻の体験を検証し、答え合わせをしてみました。記憶はおぼろげであり、記憶違いもあるかもしれませんが、妻の体験は、整理すると次のようなものでした。
- 時期は小学生の頃(昭和58年~昭和63年)
- 床下浸水(床上浸水の一歩手前くらい)を少なくとも2回以上経験した
- トイレに水を流したら上手く流れず、水面が上がってきた
- 水が引いたら、トイレの水も引きいつもどおりに戻った
妻の実家は、熊本市内を流れる白川の左岸の平野部にありますが、「堤防から川の水があふれてはいない」という記憶から、妻が体験した浸水被害は、外水氾濫ではなく、内水氾濫によるものであったと推測できます。
また、白川の左岸である熊本市南部は、昭和62年から下水道の処理区域になりました。義母の記憶によれば、実家が下水道に接続したのは「平成に入ってから」とのこと。ちなみにこの処理区域の下水道は分流方式です(5)。
これらの情報を総合すれば、妻が浸水被害を経験した当時、実家は【1】の「公共下水道に接続していない」状態だったと言えます。おそらく、トイレに流したし尿は、浄化槽を経由して、道路側溝へ放流されていたはずです。辺りが床上の一歩手前まで浸水すれば、浄化槽や排水管は満水となります。その状態で、あらたにトイレで水を流せば、生活排水管路内の水位はさらに上がり、便器からあふれそうになるのは当然です。
おぼろげであった妻の記憶が、「どうやら正しそうだ」ということが分かりました。
(5) 熊本市上下水道局編『熊本市の下水道』熊本市,令和元年度版,2019年11月,5-12頁
ポイントは「下水道条件」と「サイン」
「豪雨時にトイレ等から排水が逆流する」というリスクの高さは、一体どの程度のものか。この問いについて、リスクは一様ではなく、アセスメント(評価)には、個別の条件が必要であるということを、ご理解いただけたのではないかと思います。
では、「水のうなどの対策は、本当に必要なのか」という問いには、何と答えるか。「対策するに越したことはない」という答えでは「大味が過ぎる」と批判した私です。もう少し繊細な味付けにこだわってみましょう。ポイントは「下水道条件」と「サイン」です。
下水道条件が【1】または【2】の場合は、「豪雨時には、排水逆流のリスクが相当に高まる」と評価できます。水のうなど、然るべき対策の実施をお勧めします。
下水道条件が【3】の場合が悩ましい。悩ましいながらも、せめて頼りにしたいのが、リスクを知らせる「サイン」です。2)の逆流は、実は1)の逆流のリスクの高まりを知らせるサインだと言えます。幼い頃の妻はこのサインを受け取り、「なんかヤバい……」と直感的に理解していました。また、便器に溜まっている水──「封水」と呼びます──が波打ったり、ポコポコと音を立てたりすることも、同様のサインと言えます。
これらのいずれかのサインをキャッチをしたら、そのときは迷わず水のうを作り、1)の逆流による被害を未然に防いでください。ちなみに、これらのサインは【3】だけでなく【1】【2】の場合でも、対策実施のトリガー(きっかけ)として利用が可能です。
また、水のうを置くべき排水口は、トイレだけではありません。逆流によるあふれは、物理的な理由から、より低い位置にある排水口から起きやすいのです。浴室の洗い場や洗濯機用の排水口こそが、むしろ優先的に水のうを置くべき場所と言えます。
というわけで、ここから先は一般論では答えられません。なので遠慮なく、個別に質問してください。
今日のメッセージ
リスクは一様でなく評価には個別の条件が必要
一般論では答えらず、個別に質問してください
長谷川高士「リスクは一様でなく、評価には個別の条件が必要」『メールマガジン【前進の軌跡】』第216号,2022年6月21日(2022年7月2日改稿)
引用・参考文献一覧
- 愛知県「豊山町(豊場地区)の下水道利用制限のお願いについて(ページID:0404368)」,2022年6月6日(https://www.pref.aichi.jp/press-release/toyoyama-gesuiseigenn.html,2022年7月2日情報取得)
- 気象庁「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html,2022年7月2日情報取得)
- 熊本市上下水道局編『熊本市の下水道』熊本市,令和元年度版,2019年11月,5-12頁
- 時事通信社「「内水氾濫」ハザードマップを=広域浸水受け、自治体に通知―国交省」『時事ドットコム』,2019年11月9日(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_disaster20191109j-03-w280,2022年7月2日情報取得)
- 毎日新聞社「下水道トラブル 5000世帯に排水減要請 愛知・豊山」『毎日新聞デジタル』,2022年6月8日(https://mainichi.jp/articles/20220608/ddq/041/040/003000c,2022年7月2日情報取得)
- 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年