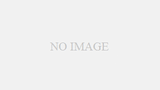メルマガ第211号(1)では「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」というタイトルで、相談について書きました。結びの文章の一部を引用します。
「でもね、」と、妻は言います。
「何に困っているのかを説明できるのならば、もっとみんな救われているの」答えのある疑問は解消できる。
悩みの答えは引き出される。妻は、鋭敏さと柔らかさを合わせ持つその豊かな感性で、言葉にならない言葉を言葉ではないままに感じ取り、それを言葉にすることができる。言わば「相談」ならぬ「創談」ができるのです。悩みを引き出す創談から、答えを提供する相談へ。私たちの2人の未来のイメージの輪郭が、また1つハッキリとし始めました。
最初に伝えるメッセージは決まっています。
「なんでも言って、ぜんぶ聴くよ」(1)
今日は、先月気づいた「創談から相談へ」について、この1か月で感じたことについて書きます。
(1) 長谷川高士「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」『前進の軌跡』第211号,2022年
相談受付、はじめました
同号で紹介した「専門家にチャットで相談できるサービス」。愛猫の体調不良をきっかけに、私たちはこのサービスを見つけました。相談に乗ってくれた獣医の対応に満足した私。
「あの獣医さんみたいに、自分も誰かの安心に貢献したい」
そう思って「水回り修理の専門家」としてサービスへの専門家登録を申請し、無事採用されました。
同時にもう1つのサービスにも登録しました。自分のスキル(技能)をサービスとして提供したい人と、そのサービスを購入したい人を引き合わせるマッチングプラットフォームです。もともとこのプラットフォームには購入者として登録をしていましたが、サービスの提供者としても、この度登録したわけです。提供するサービスは、同じく「水回り修理の相談」です。
「トイレや水回りの相談に丁寧にお答えします!」
こう題して商品を出品しました。
両者に登録してから約1か月。昨日までにチャット相談サービスで9件、マッチングプラットフォームでの購入が1件あり、合計10件の相談に答えました。いずれのサービスも相談者から5段階の評価──いわゆる「星いくつ」という“あれ”──を受けます。これまでのところ、私の答えや応対には満足してもらえているようです。
やっぱり、相談されるのが好き
同号の冒頭では、こんなことを書いています。
「相談されるのが好き」
「相談を受けたい」
そんな自分の気質に、最近あらためて気づくことがありました(3)。
10件の相談に答えて、あらためて思うことは、「やっぱり、相談されるのが好き」ということでした。相談があればメールで通知が届きます。その通知が届くと、ワクワクします。いずれのサービスも、原則は文字チャットでのやりとりです。相談者の相談内容をしっかりと読み取り、適切な回答を返す。できるだけ誤解が生まれぬよう、表現を丁寧に工夫する。この作文作業が何より楽しく、ある種スリリングでもあるのです。
「あー、それは私にとっての“車の運転”みたいなもんだねー」
相談に答える作業の楽しさを「それって、どんな感じ?」と尋ねた妻に、「ゲームみたい」と答えたところ、妻がこう言って自分の感覚との重なりを教えてくれました。妻いわく、
「運転はテトリスみたいで気持ちいい。まわりの車の状況を把握して予想して、車線変更とかが“バシッ”と決まるとちょー気持ち良いの」
と。対象こそ違いますが、「その感覚は、近い!」と、私も思いました。相談に答えきった時、私も気持ち良いのです。
(3) 長谷川、前掲「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」
相談者の「分かって欲しい」に応える
再び同号からの引用です。
対話の中で、相談する人の心理には「分かって欲しい」という気持ちがある、と2人で気づきました。そして、今日この文章を書きながら、あらためてそのことに気づき直しています。
意見を求める側、与える側のいずれであっても、私は「恐れ」と「安心」という感情に鋭くフォーカスしている。
「分かってもらえないのではないか」という恐れ。
「分かってもらえた」という安心(4)。
まだわずか10件の相談ではありますが、それらのすべてに「分かって欲しい」という心理を感じました。ゆえに回答の際には「分かってもらえた」という安心を提供することに心がけています。相談の文中には、疑問形で書かれた文章がいくつかあります。それらは相談者が抱えている疑問を表しています。ところが前提に誤解があり、その疑問そのものが的外れであることも、ときにはあります。
そんな場合でも、疑問や質問には必ず率直に答えるようにしています。前置きや言い訳をせず、できるだけストレートに、です。たとえ誤解があったとしても、抱えている疑問は、その人の素直な思考。それに率直に答えることは、「疑問を抱えているあなたを受け入れます」という何よりも分かりやすいメッセージだからです。
疑問に率直に答えた上で、補足としてやんわりと誤解を解くための情報を伝えます。回答の文章としては長くなりますが、ある程度の文量までは、短いよりも長い方が相談者の満足度は上がるようです。丁寧な対応が安心につながるのではないかと推測しています。
(4) 長谷川、前掲「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」
文字チャットでも十分成立する
上の2つは「想像していたことが想像どおりだった」という話でした。次は、想像していなかったことです。それは、相談が文字チャットでも十分成立し得る、ということ。同号でも書いたとおり、「水回り修理のオンライン相談」というサービスを自社で準備中です。その際の相談方法は、「Zoom(ズーム)」などのビデオチャットを想定していました。トラブルの状況をスマートフォンで撮影してもらいながら、相談に応じることを想像していたからです。
このサービス自体は未試行のため、需要の有無や有効性は検証できていません。しかし「分かって欲しい」という相談者の心理を考えると、相談の入口がビデオチャットである必要はなく、むしろ文字チャットの方がハードルが低いのではないか、と体感的に検証ができました。そして、相談者への「安心」の提供は文字チャットでも十分可能でした。
文字チャットと言っても、「LINE(ライン)」のトークのように画像などのファイルを添付することができます。すでに受けた相談の中にも、トラブルが発生している箇所の写真を相談者に撮影していただき、それをもとにコメントした事例があります。画像を見た分だけ私の回答にも説得力が増すため、相談者の安心感がより高まったことを感じました。
「当然」という文化を創ることもまた「創談」
1か月で10件の相談を、多いと見るか、少ないと見るか。私は「少ない」と見ています。チャット相談サービスでの花形は医師や弁護士、獣医師です。また医療や法律に関するチャットサービスは、他にもたくさんあります。「相談を受け付けてもらえる場所がきっとある」という感覚が、
医療や法律に関しては広がりつつあるのだと思います。
翻って水回り修理は、どうか。「相談を受け付けてもらえる場所がきっとある」という感覚は「ほとんど持たれていない」というのが実状でしょう。もう少し踏み込んで言えば、「相談だけを受け付けてもらえる」とは思っていない、あるいは、「相談だけなど受け付けてもらえるはずがない」と無意識的に思い込んでいる、という状態だと言えます。ひと言で言えば、「そういう文化がない」のです。
これは、妻と2人でそこを目指して進んでる児童福祉の現場も同じこと。「もっと早く、もっと手前で、もっと身近な人同士が手を差し伸べられるような社会」であるためには「相談するのが当然」という文化が必要です。悩みを引き出す創談(5)から、答えを提供する相談へ。「相談するのが当然」という文化を創ることもまた「創談」なのかもしれません。
水回り修理の相談サービスを通じて、この創談にチャレンジしてみようと思います。
(5) 長谷川、前掲「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」。「創談」は筆者らによる造語。
今日の気づき
相談は、文字チャットでも十分成立し得る
「当然」という文化を創ることもまた「創談」
長谷川高士「「当然」という文化を創ることもまた「創談」」『メールマガジン【前進の軌跡】』第215号,2022年6月14日(2022年7月3日改稿)
引用・参考文献一覧
- 長谷川高士「悩みを引き出す創談から答えを提供する相談へ」『前進の軌跡』第211号,2022年