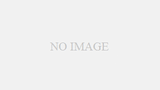「さて、何を書こう」
今朝は久々に、こう思いながら書いています。
もともと「書きたい」と思って準備を進めていたネタがあったのですが、進めるうちに「この程度の準備では、まだ書くべきではない」という結論に至り、見送ることにしました。
見送ったはいいものの「さて、どうしよう」と困ったわけです。
これまで私は、メルマガを200本以上書いてきました。文章の書き方は人それぞれ。私の場合は、書きながら、そして文字になったそれらを読みながら考えを進め、そしてまた書き進めるというスタイルです。
ゆえに、テーマとざくっとした全体像をイメージして書き始めても、自分がタイプした文字につられて、当初のイメージとは別の方角に向かうこともよくあります。これが「プロット」と呼ばれる筋書きや構成の段階でできると効率が良いのでしょうが、どうにも私はそれが苦手なようで、それだと気分が乗らないのです。書きながら考え、考えながら書く。これが私の書き方であり、これが心地良いのです。
──と、書いているうちに、すでに自らが書いた文章に引っ張られていました。悩みながらも「これにしようか」と決めたものとは別の内容である「文章の書き方」について書き進めていました。そのまま進めても良いのですが、あえて戻してみようと思います。
「これにしよう」と決めたものは「分析と解析」です。今、目の前に分析と解析が必要な膨大な量の情報があり、これを「分析しよう、解析しよう」と向き合っている私がいます。ここで私が言う「分析と解析」とは、一体何か。私がやろうとしており、実際にやるであろう具体的な作業を皆さんに紹介する形で、私の書き方、ならぬ「私の分析と解析の仕方」をあらためて見つめてみようという企てです。
いつにも増して──いや、いつも通りかもしれませんが──「素っ頓狂なこと言ってるな」と思われるかもしれません。よかったら、お付き合いください。
前提の話 ─語釈と対象データ─
まずは、いつも通り「分析」と「解析」の語釈を確かめます。広辞苑(1)を引きました。
ぶん‐せき 【分析】
ある物事を分解して、それを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること。かい‐せき 【解析】
解析:物事をこまかく解き開き、理論に基づいて研究すること(1)。
両者の関係性に注目しつつ、これを平たくまとめると、次のように言えるでしょうか。
「分析で細かく分けた要素から、論理的に何らかの答えを導き出すのが解析」
「そうそう、やろうとしていることはこれ!」と我が意を得たりの気分です。私がやりたいことは語釈的にも「分析と解析」で合っているようです。
次は「目の前にある膨大な量の情報」の話です。
昨年(2021年)10月に発生した和歌山県和歌山市の断水事故をきっかけに、その調査を目的とした公文書開示申出を、同市に対して行いました。2度にわたり、合計13件の公文書の開示を申し出ました。
和歌山市は、公文書開示の請求権者を「和歌山市民」としており、請求権者である和歌山市民によって行われる当該手続きは「開示請求」と呼ばれています。私は和歌山市民でありません。ゆえに私は請求権を有していない。しかし、同市の条例は、非請求権者からの申出についても、「これに応ずるように努めるものとする」と定めていて(2)、同市は「手続については、開示請求に準じて行います」とこれを補足し(3)ています。というわけで私も求めに応じてもらえました。私のような非請求権者が行う手続きは「公文書開示申出」と呼ぶのだそうです。
目の前にある膨大の量の情報は、13通の開示公文書の中で、最後に開示された文書です。対象区域内では、断水をきっかけに様々な支障が発生しましたが、その1つが主に給湯器や温水器など水回り機器の故障でした。和歌山市は「審査が必要」としながらも、「これを補償する」と発表し、申請を受け付けました。13通目の開示公文書は、この機器補償の申請内容の一覧です。
申請の総数は1082件。A3版の一覧表は、小さな文字で記されているにもかかわらず、全部で88ページもありました。この膨大な量の情報を分析し、解析しようというわけです。
(1) 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年
(2) 和歌山市情報公開条例(平成5年条例第33号)第22条,最終改訂2016年
(3) 和歌山市総務局総務部総務課 「情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書」和歌山市,令和2年度版,2020年,3頁
分析 ─細かい要素に分ける─
まずは一通り、1082件の申請内容に目を通します。後の作業も見据えて、紙で受け取った資料をスキャン(画像読取)して電子データ化します。文字をテキストデータに変換する「OCR」と呼ばれる処理をスキャンと同時に行うのですが、今回のデータは文字サイズが小さ過ぎて上手く変換されませんでした。スキャンしてPDFデータに変換した資料を画面上で読み進めました。
1082件もあると、読み進めるだけでも集中力を要する作業でした。個人情報は「黒塗り」されていますが、申請日と機器の故障状況は確認できました。申請日の昇順で並べられたデータを眺めていると、いくつかの傾向が見えてきます。想像していなかった「意外な結果」をすぐに見つけることができました。
その「意外な結果」の1つが気になり、「なぜ、そうなったのか」という原因を一旦探ってみることにしました。気になった意外な結果とは「エコキュートや電気温水器の空焚き」です。少なく見積もっても全体の1割である100件程度は、この現象が起きていることが見て取れました。
「空焚き」とはどのような現象かを調べました。すると、機器の構造上では「断水しても空焚きは起きないはずである」ということがわかり、ますます謎が深まりました。私にとって「心地良い瞬間」です。謎を解きたくなる衝動が、フツフツと沸き上がるのを感じるのです。この謎解きに数歩だけ足を踏み入れてみました──が、想像以上に深いことがわかり、一旦引き返しました。
ここが現在地。
以降は、これから予定している作業です。
OCR処理に失敗したため、人力でデータ化します。文字を目で読み取り、手でタイプ入力するのです。地道であり、膨大な時間がかかりそうですが、後の「解析」の効率を考えると欠くことのできない作業です。この時、解析時に役立つように、必要と思われるラベルを各行のデータに付加していきます。そして、この作業過程で見つかる違和感や疑問についても、先の空焚き同様に謎解きを進めます。
解析 ─論理的に答えを導く─
エクセルなど表計算ソフト上でデータ化された情報を、付加したラベルを活用して集計し、傾向
や特徴をあぶり出します。この時、謎を解いて得た答えが集計の1つの評価軸として役立つこともあれば、集計によってあぶり出された傾向や特徴が、謎解きのヒントになることもあります。このように分析と解析の往還を繰り返しつつ、段階的に精度を高めていき、最終的に答えを導く。言葉にしてしまえば、あっさりした内容になりますが、実のところ「やってみなければ分からない」というのが分析と解析の醍醐味でもあるわけで、その醍醐味を文章で表現しきれていない己の文章力の限界にもどかしさを感じます。
というわけで、「いつになる」という時期の約束はしませんが、この分析と解析の結果も本メルマガで披露したいと思っています。興味がある方は、どうぞご期待ください。
骨が折れる分析も、解析のためなら頑張れる。自分がやっていること、やろうとしていることを分析し解析して得た、これが今日の気づきです。
今日の気づき
分析で得た要素から論理的に答えを導くのが解析
骨が折れる分析も、解析のためなら頑張れる
長谷川高士「骨が折れる分析も、解析のためなら頑張れる」『メールマガジン【前進の軌跡】』第214号,2022年6月7日(2022年7月3日改稿)
引用・参考文献一覧
- 和歌山市情報公開条例(平成5年条例第33号)第22条,最終改訂2016年
- 和歌山市総務局総務部総務課 「情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書」和歌山市,令和2年度版,2020年
- 『広辞苑』岩波書店,第7版,2018年