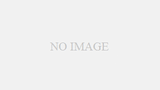第197号から199号までと第207、208号で水道水について書きました。今日はその続きを書きます。
「もしも水道水が基準を満たさなかったら、私たちがその市区町村の住民ならばどうなるでしょうか」
この問いに対する論考を続けています。過去5回をダイジェストでおさらいします。
難解な助言を読み解く過程は、いよいよ消毒へ
水を供給し続けなければならない。
水が安全でなければ、直ぐに止めなければならない。
相反するこの2つの義務を、水道の供給者(水道事業者)は法的に負っています(1)。
「基準を満たさず、水道水が安全でないかもしれない」
もしもこう気づく事態が起きてしまったら、水道事業者の責任者(水道技術管理者)は、相反する2つの義務に挟まれてジレンマに陥ります。
このジレンマの“答えらしきもの”である、平成15年(2003年)に示された「水質異常時の対応について」(2)という国による技術的助言(3)。法令ではなく助言であり、直接的に国民の権利・義務に影響を及ぼしてはならないがゆえに、その内容は難解でした。
ジレンマに陥った際の水道技術管理者の判断は、私たち住民にとっても一大事。その判断を批判的(クリティカル)に評価する視点が必要であり、場合によってはその是非を問わねばなりません。そのために私は、住民の1人としてこの難解な助言を「読み解きたい、理解したい」と思いました。
実際に、難解な助言を読み解き、理解するために水質基準についてあらためて学びました。200年前に生きた偉人らに学び、一般細菌と大腸菌は、基準に満たねば直ちに給水を停止すべき項目であることを知りました。そして基準を満たすために必要な浄水処理を次のようにまとめました。
水質基準を満たすためのポイントとして、これらの条文は次の3つにまとめられます。
- 1)原水には、たくさん汲める良い水を選ぶこと
- 2)必ず塩素で消毒すること
- 3)必要ならば、沈殿やろ過をすること(4)
これらのうち、1)と3)について直近の2回(第207号、208号)で深掘りしました。残る2)の「必ず消毒すること」について、今日は書き進めたいと思います。
(1) それぞれ水道法(昭和32年法律第177号、平成30年法律第92号による改正)第15条第2項、第23条に規定。
(2) 厚生労働省健康局水道課長「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日健水発第1010001号〔最終改正 令和4年3月31日薬生水発0331第1号〕)。いわゆる「課長通知」の1つ。
(3) 「技術的助言」とは地方自治法(昭和22年法律第67号、令和3年法律第50号による改正)第245条の4第1項等に規定されるもの。平成23年(2011年)3月の国会質疑等を踏まえ、同年7月6日に総務省大臣官房長から内部部局長に発出された文書「今後発出する通知・通達の取扱いについて」において「技術的助言として発出する場合には、その旨を通知に明示すること」と、あらためて周知を図られたものであり、平成15年(2003年)時点の当該通知にその明示はないが、その内容から「(情報提供するにとどまらない)技術的助言」であると筆者が判断した。
(4) 長谷川高士「原水には、たくさん汲める良い水を選ぶこと」『前進の軌跡』第207号,2022年
塩素消毒は法律で決まっているとおりにする
水道法や省令は、水道水の消毒についてどのように規定しているでしょうか。水道事業者の「講ずべき措置」を規定している法令の内、消毒に関する部分を再度引用します。
水道法(昭和32年法律第177号、平成30年法律第92号による改正)
(施設基準)
第5条 水道は、(中略)全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
四 浄水施設は、(中略)浄水を得るのに必要な(中略)設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。(衛生上の措置)
第22条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号、令和3年厚生労働省令第88号による改正)
(衛生上必要な措置)
第17条 法第22条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号
に掲げるものとする。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(中略)以上保持するように塩素消毒をすること。(後略)
これらから、次の2つの法定義務を読み取ることができます。
- 〈1〉水道水の消毒は塩素でしなければならない
- 〈2〉蛇口での残留塩素が0.1mg/L以上でなければならない
また第208号では次の表を書き、「生物浄水の仕上げに、あえて“消毒”を書き入れました」と書きました(5)。
| 浄水種別(6) | 下ごしらえ | 浄水処理 | 仕上げ |
| 生物浄水 | 自然沈殿 | 生物ろ過 | 消毒 |
| 化学浄水 | 化学反応による沈殿 | ろ過 + 消毒 | |
生物浄水の浄水処理である生物ろ過(緩速ろ過)には、病原菌を含む細菌類を取り除く効果がある。ゆえに「消毒は不要」だとも言えます。しかし、〈1〉〈2〉のとおり、現行の日本の法律では塩素消毒が義務づけられていることから、「あえて書き入れた」のです。
では「水道水を塩素で消毒する」とは、そもそもどういうことなのか。
これまで見てきた他のものと同様に、詳しく紐解きたかったのですが、この塩素消毒だけはどうにも判然としませんでした。
塩素消毒が狙っている効果については、その科学的な立証が十分になされています。消毒とは、「感染症を惹起しえない水準にまで病原微生物を殺滅または減少させること」(7)ですが、塩素により微生物の数が減り、「感染症を惹起しえない」という消毒が期待する水準にまでそれが達することは、後に述べるとおり、100年以上前に確認されています。
その一方で、水道水に塩素を添加することには様々な副作用があり、それも含め塩素消毒には否定的な評価もあります。
「答えを明確にできそうにない」
これが「塩素消毒の必要性の程度」についての現時点での私の理解です。よって、水道水の塩素消毒は「法律で決まっているとおりにする」というのが結論となります。
「そうとしか言えない実状」について、そのいくつかを1つずつ以下に紹介します。
(5) 長谷川高士「一般呼称を手放して捉え直すと、本質が見える」『前進の軌跡』第208号,2022年
(6) 長谷川,前掲注(5)。筆者の造語で、「生物浄水」「化学浄水」は、それぞれ「緩速ろ過」「急速ろ過」のことを指す。
(7) 株式会社タンクル「滅菌(めっきん)」『ナースタ国試対策アプリ』(https://nursta.jp/kokushi/word_detail/?word_id=2214,2022年7月4日情報取得)
世界共通……ではない塩素消毒への姿勢
塩素消毒の必要性の「有無」については、現在の日本の大部分で「必要性有り」と明快に答えることはできます。それは次の2つの理由からです。
- 【1】原水の約75%を占める地表水(8)の汚染が深刻(9)
- 【2】化学浄水である急速ろ過が全体の約77%(10)
地表水の汚染度と急速ろ過の機能を鑑みれば、現在の日本では、急速ろ過で浄水した地表水が塩素消毒なしで水質基準を満たすことは「ほぼ間違いなく、ない」と言えます。【1】および【2】のとおり、日本の大部分で「地表水を急速ろ過で浄水」して給水しているわけなので、そこでは「塩素消毒が必要だ」と明快に言えるのです。
逆に言えば、それ以外の条件、すなわち「地下水を原水としている」または「緩速ろ過で浄水している」場合には、塩素消毒をしなくても水質基準を満たす可能性は想定され得ます。しかし、水道法令は一律に塩素消毒を求め、蛇口から出る水の残留塩素の値に下限を設けています。
その理由として、次の2つが挙げられます。
- 《1》浄水場での消毒後でも、配水パイプを通って蛇口から出るまでの間に病原性微生物に汚染されるリスクがある
- 《2》消毒に作用すると変化しその効果を失う塩素が有効な状態で残っていることは、それ以前の消毒が十分に作用したことを証明する
《1》および《2》は、ともに「保険的意味合い」ですが、《2》の方が特にその性格が強いと言えます。残留塩素が一定程度(省令は0.1mg/Lと規定)測定されることが、蛇口から出る水の水質の担保になり得るのです。
「塩素が有効に残っているから、安心ですよ」
と。
ところがこの保険的発想、実は世界共通ではありませんでした。このことが『水道の文化─西欧と日本─』(11)という書籍に詳しく紹介されています。
著者は「単科の医科大学勤務の西洋史学者」という異色の研究者で、下水道の歴史を衛生学の見地から、西欧と日本の違いにも着目しつつ研究していました。欧州視察の際、「つけたり(原文ママ)のつもり」で調査した上水道の「ヨーロッパに共通の在り方」に驚き、「日本と対比してみたい」としてまとめられたのが同書でした(12)(13)。
同書の内容のごく一部を大胆に要約すると、次の表のようにまとめられます。
| 国・地域 | 塩素消毒への姿勢 | 蛇口の水を直に |
| ヨーロッパ | 消極的 | 飲まない文化 |
| アメリカ・日本 | 積極的 | 飲む文化 |
塩素消毒への姿勢の違いは、日本と対比したときにより際立つ「ヨーロッパに共通の上水道の在り方」のあらわれの1つである、というのが著者の見解です。また、塩素消毒への姿勢と蛇口の水を直に飲むかどうかという文化的傾向との間にも相関があると受け止めています(14)。
著者の見解の妥当性に拠らず、塩素消毒への姿勢には地域による違いが明らかに見られます。そして著者の見解に従えば「一律に塩素消毒を求め、蛇口から出る水の残留塩素の値に下限を設ける」という日本(やアメリカ)のやり方は、少なくとも世界共通の価値基準に基づくものではない、と言えます。
なお、誤解を避けるために補足をすると、欧州の水道水は「飲まれない」のであって、「飲めない」のではありません。パリやウィーン、チューリッヒでは「水道水は飲めます」とする公共広告を見かけるそうで、この広告の存在が「飲めるけど、飲まれない」という事実を雄弁に物語っています(15)。
(8) 日本水道協会編『水道のあらまし』日本水道協会,第6版,2015年,33頁。平成24年度の実績(「水道統計の経年分析」)によるもの。河川水25.5%、ダム水46.9%、湖沼水1.5%を合計した73.9%が正確な値。
(9) 同書,68-75頁。当該箇所は「水源水質の保全」についてまとめたものであるが、裏を返せば保全に努める必要があるほど汚染されていると言える。
(10) 日本水道協会,同書,97頁。平成24年度の実績(「水道統計の経年分析」)によるもので、77.7%が正確な値。
(11) 鯖田豊之『水道の文化─西欧と日本─』新潮社,1983年
(12) 鯖田,同書,284-285頁
(13) 鯖田豊之『水道の思想 都市と水の文化誌』中央公論社,1996年,6-24頁。当該箇所にて、自著である前掲注(10)の著作に至る経緯について言及。
(14) 鯖田,前掲注(10),110-132頁。「ヨーロッパの上水道が塩素消毒をまったくしなかったり、塩素注入量がいちじるしくすくなかったりで、給水栓残留塩素の考え方が定着しなかったのは、ひとつにはフロー的なものをできるだけ排除しようとするこうした姿勢からもきているのではなかろうか。かならずしも水道水を生のままで飲むかどうかだけでは説明しきれない」とあり、水道水を直に飲むかどうかという文化的傾向との相関を認めつつ、本質は別のところにあると著者は考察している。
(15) 鯖田,前掲注(10),125頁。鯖田,前掲注(13),222-224頁
水道水の塩素消毒の歴史
消毒の歴史は1774年に、スウェーデンのカール・ヴィルヘム・シェーレが塩素を発見したことで始まります(16)。80年後の1850年代に微生物に対しての殺菌力が認められ、1886年に米国公衆衛生協会が、殺菌剤として「次亜塩素酸ナトリウム」を使うことを発表しました(17)。
水道水への塩素消毒も同時期である上水道の普及に合わせて徐々にはじまったようですが、沈殿やろ過に比べて記録や研究が少なく、情報が曖昧でした。
戦前、戦中の日本における水道水の塩素消毒事情は、結果としてどちからと言えば欧州に近い状態だったと言えます。変な言い方ですが、積極的に「消極的であった」のではなく、「積極的とまでは言えない」状態に結果としてありました。塩素消毒や水道そのものの普及度合いが低かったこと、残留塩素という概念まではその必要性をもって受け入れられてはいなかったことが、その理由です(18)。
当時の世界で異端とも言えるほどに、塩素消毒への強いこだわりを持っていたのがアメリカでした(19)。
終戦後、連合国はGHQを置いて対日占領政策を実施します。占領軍の命令が最高司令官から日本政府に出され、日本政府が責任をもって施行する間接統治方式でした。占領軍にはイギリス連邦軍もわずかばかり参加しましたが、その大部分はアメリカ軍であり、事実上のアメリカによる単独占領といえるものだったことは説明不要でしょう。
ポツダム勅令により、GHQの命令は超法規的で、かつ絶対的な性格をもっていたため、あらゆる政策がアメリカの影響を受けることになります。日本における水道水の残留塩素濃度の基準設定とその測定は、この時にGHQからの命令によって始まり、現在に至ります──。
現在の日本の水道水にとって塩素消毒は不可欠です。残留塩素があることで安心して水を飲むことができ、水系感染症の大幅な減少(20)など塩素消毒が公衆衛生上で果たしている役割は決して小さくはありません。ただし、唯一絶対の方法なわけではない。鯖田教授の論考は、私たちがそれに気づくきっかけを提供してくれています。
「答えを明確にできそうにない」
この私の理解は、こうして生まれました。はっきりさせたい気持ちが人一倍強い私ですが、不安定で不明確な状態をあえて引き受けることも大切だと気づきます。
さらに、塩素消毒は「これさえあれば大丈夫」という万全万能の方法でもありません。最後に、それにまつわる3つの補足を紹介して終わります。
(16) 古田雅一「人類と微生物の『知恵比べ』 殺菌・消毒の歴史」ヘルシストvol.249,2018年5月
(17) 日本食品洗浄剤衛生協会「殺菌・消毒に活躍する次亜塩素酸ナトリウム」食洗協シリーズNo.6,2002年
(18) 日本水道協会,前掲書,87-94頁。鯖田,前掲注(10),104頁
(19) 鯖田,前掲注(10),104頁
(20) 日本水道協会,前掲書,26-30頁
塩素消毒にまつわる補足
塩素消毒にまつわる補足です。
1つ目は「実はよくわかっていない」という話
塩素による消毒効果は、塩素の持つ酸化力の強さによってもたらされます。「酸化」とは物質が電子を失う化学反応のことで、酸化力が強い塩素は、他の物質から電子を奪う力が強い、ということです。
酸化するとなぜ微生物の細胞が失活するのか、すなわち塩素の殺菌作用の機序(メカニズム)は、どうやら未だに「よくわかっていない」ようなのです。塩素消毒はその効果の実績をもって、進められてきたと言えそうです。
2つ目は、トリハロメタン
トリハロメタンは、ある性質──メタンを構成する4つの水素原子のうち3つがハロゲン(塩素、臭素あるいはヨウ素)に置き換わる──を持つ化合物の総称です。原水中に有機物が含まれていると、消毒に用いた塩素と反応して非意図的に消毒副生成物として発生します。現在の水質基準ではトリハロメタンに上限値を設けて規制しており、その対象となるのはクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、トリブロモメタンと、こられの4つをまとめた「総トリハロメタン」の濃度です(21)。
なお、これら4つのトリハロメタンの内、クロロホルムとブロモジクロロメタンは、国際がん研究機関(IARC)において「グループ2B(ヒトに対して発がん性がある可能性がある)」に分類されています(21)。
3つ目は、耐塩素性病原性微生物
その名のとおり、塩素では殺菌されない病原性微生物です。その1つがクリプトスポリジウムという単細胞の微生物(原虫)です。
クリプトスポリジウムは、人やその他の哺乳動物の小腸に寄生して、下痢症の原因となります。感染者や感染動物から排せつされたクリプトスポリジウムは、オーシストと呼ばれる袋に包まれた形態で環境中に生存し、そのオーシストを経口摂取することで感染します。オーシストは熱や乾燥には弱いのですが、塩素には強い抵抗性があり、塩素では消毒できません(22)。
(21) 日本環境管理学会編『水道水質基準ガイドブック』丸善,改訂4版,2009年,81-93頁
(22) 兵庫県企業庁水質管理センター「よくある質問 クリプトスポリジウムとは何ですか?」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc08/faq/faq_ea07_00000003.html,2007年8月1日更新,2022年7月4日情報取得)
今日の気づき
不安定で不明確な状態を、あえて引き受ける
塩素消毒は法律で決まっているとおりにする
長谷川高士「不安定で不明確な状態を、あえて引き受ける【もしも水道が……6】」『メールマガジン【前進の軌跡】』第213号,2022年5月31日(2022年7月14日改稿)
引用・参考文献一覧
- 厚生労働省健康局水道課長「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日健水発第1010001号〔最終改正 令和4年3月31日薬生水発0331第1号〕)
- 鯖田豊之『水道の文化─西欧と日本─』新潮社,1983年
- 鯖田豊之『水道の思想 都市と水の文化誌』中央公論社,1996年
- 株式会社タンクル「滅菌(めっきん)」『ナースタ国試対策アプリ』(https://nursta.jp/kokushi/word_detail/?word_id=2214,2022年7月4日情報取得)
- 日本環境管理学会編『水道水質基準ガイドブック』丸善,改訂4版,2009年
- 日本食品洗浄剤衛生協会「殺菌・消毒に活躍する次亜塩素酸ナトリウム」食洗協シリーズNo.6,2002年
- 日本水道協会編『水道のあらまし』日本水道協会,第6版,2015年
- 長谷川高士「原水には、たくさん汲める良い水を選ぶこと」『前進の軌跡』第207号,2022年
- 長谷川高士「一般呼称を手放して捉え直すと、本質が見える」『前進の軌跡』第208号,2022年
- 兵庫県企業庁水質管理センター「よくある質問 クリプトスポリジウムとは何ですか?」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc08/faq/faq_ea07_00000003.html,2007年8月1日更新,2022年7月4日情報取得)
- 古田雅一「人類と微生物の『知恵比べ』 殺菌・消毒の歴史」ヘルシストvol.249,2018年5月